突然ですが、
と思っていませんか?
パーカスに入った方ならば誰しもが考えると思いますが、どちらも知っておいて損はない情報です。
この記事では、吹奏楽でパーカスに入った初心者の方はもちろん経験者の方もぜひおさえておきたい情報をまとめてご紹介します!
なぜ『パーカス』と略されるのか?

『パーカス』と呼ばれるのが嫌いっていうかたはすごく多いですよね。
だって、なんとなく『パー』と『カス』を組み合わせたような単語だから。
悪口やん!
ってなりますよね。
私もぶっちゃけこの呼ばれ方をするのはあまり好きではないです。
じゃあ、そもそもなんで『パーカッション』が『パーカス』と呼ばれるのか。
結論から申し上げますと、『パーカス』というのは英単語の1つです。
“Percussion”
というのは、『打楽器』といった意味のある英単語ですが、これを動詞にしたのが『パーカス』です。
つまり、
『叩く』を表す英単語が
“Percuss”
なんですね。
“Percussion”は”Percuss”の名詞形。
単語を名詞化する際によく使用されるのが“ion”という接尾語です。
例えば、
”Discuss”(議論する)→”Discussion”(議論)
“Act(活動する)→”Action”(活動)
”Collect”(収集する)→”Collection”(収集)
など、確かに接尾語”ion”で名詞になる単語って意外とたくさんあるなと思いますよね。
“Percussion”は実はその1種であることを覚えておくといいです!
英単語の1つだと思えば、『Percuss』と呼ばれることに納得できるのではないでしょうか?
基礎練はどれくらいするべき?

『基礎練って面倒だなぁ~』
『楽器を練習したほうが効率的じゃない?』
と思っていませんか?
確かに、基礎練ってゴムのパットをひたすら叩く練習なので好きじゃないと思う方もいるかもしれません。
しかし、基礎練こそ至高!
打楽器奏者にとって、基礎練が全てと言っても過言ではないでしょう!
基礎練のメリットには次のようなものがあります。
1. スティック(ばち)の扱いに慣れることができる
2. テンポ感を掴むことができる
3. 左手の強化
この3点について順にご説明していきます!
基礎練のメリットは?
①スティック(ばち)の扱いに慣れることが出来る

打楽器を鳴らす手段は基本的に、
① スティックを使う
② マレットを使う
➂ 手で直接
の3パターンに分かれます。(もちろん例外もあります。例えば、トライアングルを鳴らすのに使うのはビーターです。)
吹奏楽で特に要求されるのは、①と②です。
ここで、スティックとマレットによる演奏の『違い』を考えてみましょう!
1点目が、スティックとマレットの太さについて。
銅鑼やバスドラムのマレットを除けば、太さは、
スティック>マレット
です。
では、持つ部分が太いのと細いのではどちらが演奏しやすいでしょうか?
その答えは、細い方。
なぜなら、持つ部分が細ければ機動性が上がって容易に動かすことが出来、演奏上扱いやすいです。
一方で、太いものはやはり扱いにくさがあります。
2点目が、スティックとマレットを使った時の演奏上の違いについて。
その違いは、
スティック…ダブルストローク(2つ打ち)を頻繁に使って演奏する
マレット…にシングルストローク(1つ打ち)で演奏する
です!
鍵盤打楽器でダブルストロークを使うことはほとんどないですし、ティンパニでは全く使うことはありません!
1つ打ちと2つ打ちでは圧倒的に2つ打ちの方が難しく、2つ打ちを出来るようになるにはかなりの練習が要求されます。
よって、スティックの扱いの方がマレットの扱いよりも難しいです。
つまり、スティックを上手く扱うことが出来れば、マレットも十分に扱うことが出来るようになっているのです!
基礎練でスティックの扱いに慣れることによって、スネアドラムだけに限らず、様々な打楽器を演奏することが出来るようになりますよ!
②テンポ感を掴むことが出来る

吹奏楽のパーカッションパートにはどんな役目を要求されるでしょうか?
パーカッションにとって最も重要なことは、
テンポキープ
です。
なぜなら、パーカッションパートは曲の演奏においてメトロノームみたいなものだからです。
練習するときにメトロノームが壊れていたらめちゃくちゃ嫌ですよね。
急に遅くなったり、早くなったりするみたいな…(笑)
同様に、パーカッションがテンポを一定に保つことが出来ないと、最悪、曲が崩壊します。
それだけ、パーカッションは吹奏楽にとって重要といえます!
初心者は、とりあえずテンポ感を身につけることを考えましょう。
テンポ感を身につけるのに一番良い方法は、メトロノームで合わせながら何度も基礎練を行うことです。
基礎練をやっていくうちに、段々テンポ感を掴むことが出来るようになります!
様々なリズムを基礎練で練習して自分の中でテンポ感を掴み、合奏で活躍しちゃいましょう!
③左手の強化

まずは質問です。
あなたは右利きですか?それとも左利きですか?
日本人の多くは右利きです。
したがって、左手を使うことに慣れていません。(左利きの人は、右手のことだと考えてください。)
例えば、あなたは『ペンで字を書く』、『歯磨きをする』、『箸で食べる』などの動作を左手で出来ますか?
多くの人は出来ないと思います。
一方で、右手でやるなら無意識にでも出来ます。
それだけ左手は使い慣れていないのです。
したがって、初めから初心者が左手を上手く使えるということはまずありません。
打楽器奏者は誰しも、左手を強化することから始まります。
右手は普段使っているということもあり、意外とすぐに使い慣れるということも多いです。
よって、左手は右手以上に練習が要求されます。
左手の強化になにが良いか?
その答えは、基礎練をすること!
「楽器を演奏する中で左手を強化していけばいいじゃん」と思うかもしれません。
しかし、曲を演奏する際は、右手スタートで演奏するなど無意識的に右手頼りになってしまいます。
左手で何度も叩く練習をしたり、リズムトレーニングを左手から始めるなどをして徐々に左手を鍛えましょう!
最後に
いかがでしたか?
今回は、吹奏楽でパーカスに入った方に向けて知っておいてほしい情報をご紹介してきました!
もしかしたら、これを見ている人の中には不本意でパーカッションになった人もいるかもしれません。
その場合、まだ打楽器の魅力が分からないということも多いでしょう。
しかし、打楽器は奥が深く本当に面白いです。
演奏に取り組んでいくうちに、「楽しい!」という気持ちが絶対湧き上がってくるはずです!
私的には、打楽器も魅力は「打楽器アンサンブル」にあると思っています。
こちらの記事でご紹介しているので、一度見てみてください!
ぜひ参考にしてみてくださいね!
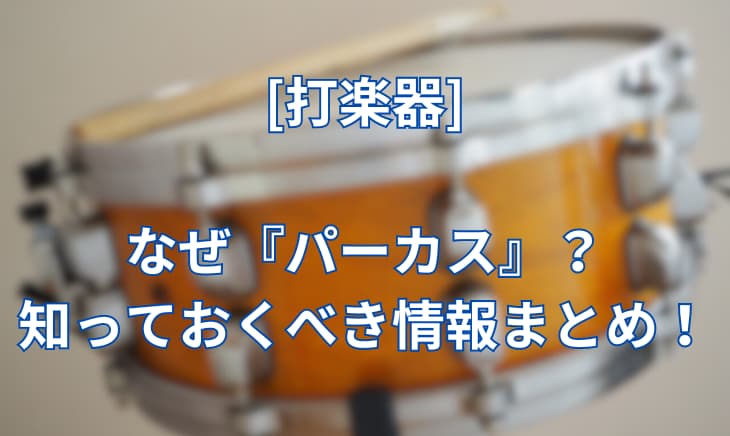











『パーカッションはなぜ「パーカス」と略される?』
『基礎練はどのくらいするべき?』